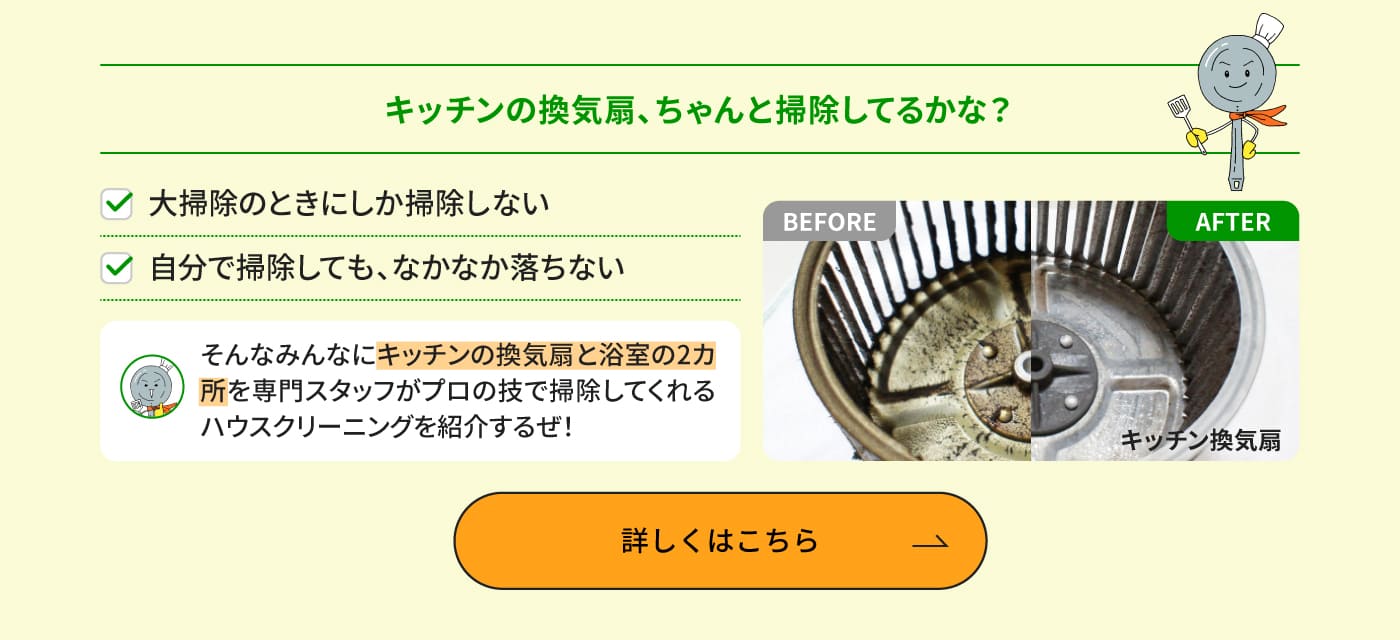味付けの基本「調味料のさしすせそ」とは?入れる順番や考え方も解説!

「うちのご飯は世界イチ」の番外編、お料理の基本をご紹介するミニレッスンへようこそ。第22回は、「調味料のさしすせそ」です。調味料を入れる順番や保存方法をご紹介します。
おさとう、ぼくがいれたい~!
じゃあ、お塩もコウちゃんに入れてもらおうかな?
確か調味料を入れるのに正しい順番があったような…。
調味料のさしすせそだな。意味を知っておくと、料理をするのがもっと楽しくなるゾ!
目次

【味付けの基本】調味料のさしすせそを入れる順番とその理由

料理の味付けの基本は、「調味料のさしすせそ」。主に和食の味付けに使う調味料の種類、また、それらを使用する際の順番が分かるように作られた語呂合わせです。
では、それぞれ何を指しているのでしょうか?
さ=砂糖
食材をやわらかくし、甘みを付ける調味料です。砂糖は、食材に味が浸透するのが遅いため、最初に入れます。湿気や臭い移りを避けるため、密閉容器に入れて常温保存します。
し=塩
食材から水分を外に出し、塩味を付ける調味料です。塩は浸透圧が高く、砂糖より先に入れると、砂糖の甘みが食材に浸透しにくくなってしまうため、砂糖の次に入れます。保存は常温で、砂糖と同じく密閉容器に入れます。
す=酢
食材に酸味や風味を付ける調味料です。酢は早く入れると酸味が飛んでしまうため、仕上がり近くに入れます。保存は常温で、開封後の賞味期限を確認しておくと安心です。
せ=醤油
大豆から生まれた、味に深みを与えて食材に香りを付ける調味料です。醤油の香りや風味を逃さないために、仕上がり近くに入れます。醤油は空気に触れると酸化してしまうため、開栓後は冷蔵保存します。
※密閉ボトルに入った醤油の場合は、酸化を防ぐ仕組みとなっているため、賞味期限を確認し、常温保存します。
そ=味噌
味をまろやかにし、食材に香りを付ける発酵食品です。加熱により香りが飛びやすいので、仕上がり近くに入れます。保存方法は冷蔵で、空気が入らないように密閉します。
「調味料のさしすせそ」に含まれていない酒やみりんは?
「調味料のさしすせそ」に混同されやすいものとして、酒とみりんがあります。この2つも、料理のレシピによく登場する基本的な調味料です。味の特徴や使い方、ほかの調味料と合わせるときの順番を解説します。
酒
料理酒は、砂糖と同じように食品をやわらかくする作用があります。また、食材の臭みを取ったり、味を染み込みやすくさせる働きもあるので、砂糖の前に加えるようにしましょう。
「料理酒」として販売されているものには、食塩や甘味料が添加されているものもあり、その場合は塩分調整が必要です。また、普通の日本酒も料理酒と同じく料理に使用できますが、食塩や甘味料は添加されていないので、自分で塩味などの味付けをします。
みりん
みりんには大きく分けて、本みりん、みりん風調味料、みりんタイプの発酵調味料の3種類があります。三者の違いはアルコール度数と塩分です。本みりんはアルコール度数が14%前後と高いため、酒のように食材の臭みを消してくれます。それに対してみりん風調味料には、アルコール分はほとんど含まれません。みりんタイプの発酵調味料のアルコール度数は商品によって異なりますが、塩分が含まれているのが本みりんとの大きな違いです。
本みりんは煮崩れを防ぐ効果があるのと、アルコールを飛ばす必要があるため、料理に使うなら砂糖よりも前に入れます。お酒と同じタイミングで入れるとよいでしょう。
みりん風調味料やみりんタイプの発酵調味料は味噌よりも後、調理の仕上げに入れることで、照りや風味が付き、味にコクが出ます。みりん風調味料やみりんタイプの発酵調味料は、料理酒と同じように食塩が含まれるため、塩分の調整には注意しましょう。
人気のキーワード
【味付けの考え方】調味料のさしすせそ
「調味料のさしすせそ」と酒・みりんには役割と特徴があります。それらを理解したうえで味付けを考えていきましょう。
「調味料のさしすせそ」と酒・みりんを入れる順番
先でも解説した通り、「調味料のさしすせそ」と酒・みりんには入れる順番があります。
1.酒やみりん 2.砂糖 3.塩 4.酢 5.醤油 6.味噌
これはそれぞれの調味料の浸透度合いや、風味の特徴を考慮したうえでの順番であり、レシピによって前後します。レシピに指示がない場合、あるいは自己流で料理するときに困った場合は、この順番で調味料を入れましょう。
美味しいと感じる味付けの濃度は一緒
人が美味しいと感じる塩分濃度は、ちょうど人間の体液(生理食塩水)と同じくらいの約0.9%だといわれています。糖分は人によって好みがありますが、甘さ控えめで2%、甘めなら5%~6%です。なお、材料の重量と調味料の分量から計算される割合を、「調味パーセント濃度」といいます。これは塩分でも糖分でも値の求め方は同様で、以下の式を使って求めることができます。
調味パーセント濃度=調味料の塩分量÷材料の質量×100
学校や病院などの施設で作業を標準化するために用いられる計算式ですが、家庭料理に活用することで味付けの失敗が少なくなったり、食材を余らせにくくなったり、といったメリットも得られます。味加減の目安として知っておくのもよいでしょう。
砂糖・塩・醤油を使った調理例
砂糖・塩・醤油は味付けの基本中の基本の調味料。特に、和食の煮物には欠かせないものといえます。ここでは、「さしすせそ」の順番を踏まえて、実際に美味しい煮物を作る手順をお教えしましょう。

和食の煮物の場合、最初に砂糖を入れて味を浸透させます。

砂糖の次に塩を入れて、味気を付けます。

塩の次に醤油を入れて、風味や香りを付けます。
特に、和食では「さしすせそ」の順番で入れると、美味しく味付けができるといわれています。
※レシピによって、入れる順番が異なる場合もあります。
【味付けの黄金比】さしすせその定番の配合は?
各調味料の特徴や入れる順番、実際のレシピなどをご紹介してきましたが、味付けのベースを押さえておけば、そこから自分好みの味付けに調整することもできます。ここでは、「調味料のさしすせそ」と酒・みりんを使った、定番の配合をご紹介します。
・基本の配合
醤油:酒:みりんを1:1:1
使用例)鶏・魚の照り焼き、きんぴらごぼう、鶏そぼろ
和食に活躍する甘辛い味付けには、この配合をベースにするとよいでしょう。鶏・魚の照り焼きや、きんぴらごぼうなどさまざまな料理に重宝します。おろし生姜やにんにくといった香味野菜を足したり、なたね油やごま油、オリーブオイルなど、使う油を変えたりすることで、バリエーションも楽しめます。
・味噌を使った配合
砂糖:味噌:酒を1:2:2
使用例)豚とキャベツの味噌炒め、ふろふき大根など
コクのある炒め物や、ふろふき大根、田楽のタレなどにおすすめです。炒め物やソテーなど手早く味付けしたいメニューの場合は、合わせ調味料として事前に混ぜ合わせておきましょう。
・酢を使った配合
砂糖:酢:醤油を1:1:1
使用例)チキン南蛮、油淋鶏(ユーリンチー)など
甘過ぎず、酸っぱ過ぎず、甘みと酸味がバランスよく仕上がり、料理のレパートリーが広がる甘酢の味付けです。チキン南蛮や油淋鶏などの下味に使う場合は、味にムラが出ないよう、よく混ぜ合わせてから漬け込みましょう。
・煮物の配合
砂糖:醤油:酒:みりんを1:1:1:1
使用例)肉じゃが、ひじき煮など
煮物の合わせ調味料の配合を覚えておくと、味が決まらないうちに煮崩れてしまったというようなことがなく便利です。
「調味料のさしすせそ」に関するよくある質問
調味料のさしすせそに関するよくある質問をご紹介します。
なぜ「調味料のさしすせそ」の「せ」が「しょうゆ」(醤油)なのか?
昔使われていた「歴史的仮名遣い」では、醤油を「せうゆ」と表記するため、醤油が「さしすせそ」の「せ」の調味料となっているといわれています。
なぜ「みそ」だけ下から文字を取るの?
サ行の最後の文字が「そ」であるため、味噌の下の文字を充てたという説が多く挙げられています。ほかにも、味噌の「噌」は日本で作られた漢字なので、この一文字で味噌という意味が通じるから…という説があります。
調味料のさしすせその順番は絶対ですか?
絶対ではありません。和食ではさしすせその順番を基本としていますが、レシピによって異なります。
砂糖とみりんはどちらを先に入れるべきですか?
本みりんであれば、先です。みりん風調味料であれば、味噌の後です。
酒とみりんはどちらを先に入れるべきですか?
酒を先に入れます。酒を最初に入れることで素材の臭みを取り除き、味を染み込ませやすくする効果があるためです。
みりんと酒を入れる理由とは?
食材の臭みを取ったり、味を染み込みやすくさせる効果があるためです。
調味料を入れる順番には意味があったんだね!
素材の美味しさを引き立てるためにも、「調味料のさしすせそ」の順番を意識することが重要なんだゾ!