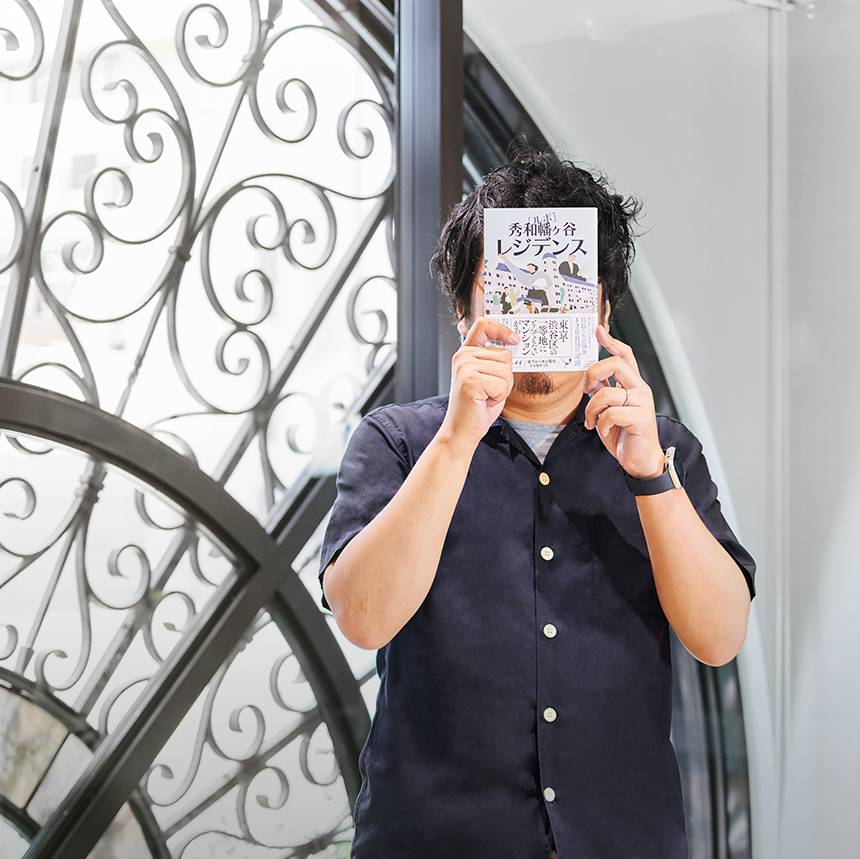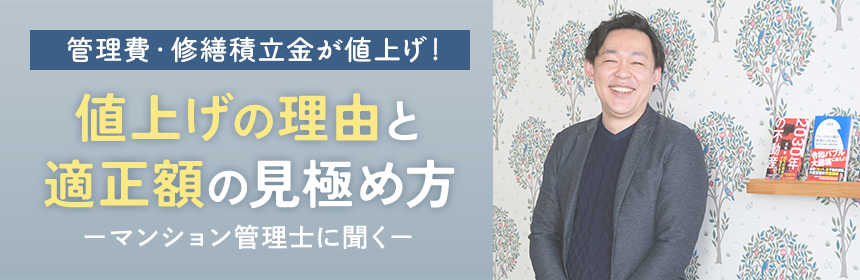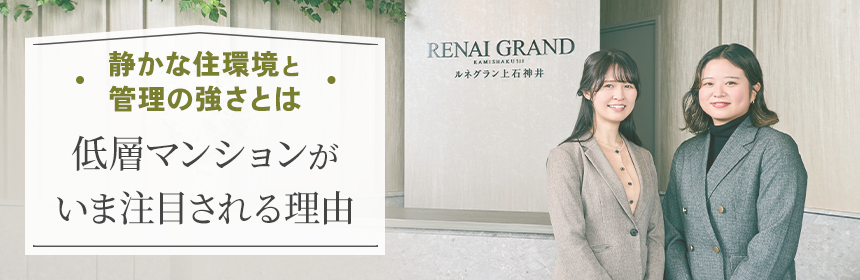地震大国日本において、マンションの耐震性能は非常に重要です。南海トラフ巨大地震など、大型地震への危機感が募る今、長谷工・技術研究所の太田雄介さんに、「耐震」・「制振」・「免震」の特性と耐震性能を高める最新技術などを聞きました。
「耐震」・「制振」・「免震」のメリット、デメリットとは?
――まず、技術研究所についてお聞きします。日々どのような研究を行っているのでしょうか。
太田雄介(以下、太田):建築構造、地盤基礎、建築環境、建築設備、建築材料、先端技術の研究室に分かれ、マンションに関するさまざまな性能実験や研究開発を行っています。具体的な研究テーマは、耐震補強、建物の長寿命化、耐震性の強化、環境問題などです。高層マンションを建設するために必要な高強度のコンクリートを開発したり、建設における生産性を向上させるための新工法を研究したり、大学との共同研究も行ったりしています。

▲長谷工コーポレーション 技術推進部門 技術研究所 建築構造・地盤基礎・建築材料研究室
統括室長 太田雄介さん ※所属・肩書は取材当時のもの
――よくマンションの耐震性能を考える際、「耐震」・「制振」・「免震」という言葉を聞きます。それぞれの違いを教えてください。
太田:簡単に言えば、現行の建築基準法を満たすために行う地震対策のアプローチ方法の違いです。
まず、「耐震」構造について。これは建物自体の強度を上げ、大地震が生じても躯体が耐えられるように設計する構造です。建物を支える柱や梁を強度が高いものにすることで、震度6強などの地震があっても倒壊せずに住人が避難できるようにするのが目的になります。
メリットとして、各ゼネコンで実績が多いこととコスト面ですね。「制振」・「免震」に比べると建設費用を抑えることができます。ただ、デメリットとして大きな揺れを感じます。
基本的に揺れに耐えるもので逃がすわけではありません。ダイレクトに地震の揺れを感じるので、室内の家具などは倒れる危険がありますし、高層階になると住民も立っていられないので机の下などに避難する必要があります。
――「制振」はどのような工法になるのでしょう。
太田:「制振」は、簡単に言うと地震などの揺れを吸収する構造です。建物内部にダンパーなどの制振装置を設置することで揺れのエネルギーを吸収します。そのため、「耐震」よりも住民は揺れを感じないというメリットがあります。
また、「耐震」構造だと、地震によって梁や柱が破損することが多いのですが、「制振」装置があればそうした被害をある程度抑えられるというのも特長です。
超高層マンションでは、「低降伏点鋼(ていこうふくてんこう)製制震ダンパー」がよく使用されています。地震時に優れた変形能力を発揮する低降伏点鋼を用いるダンパーは多いのですが、当社が開発したものは鉄筋コンクリートと相性がよく取り付けやすい。また、通常のダンパーは基本メンテナンスフリーですが、万が一不具合があった場合、取り替えは容易ではありません。その点、当社の「低降伏点鋼製制振ダンパー」は、取り外しが可能で交換もできるという特長があります。比較的ローコストで実現可能な点も優位性ですね。
――では反対に「制振」のデメリットは。
太田:「耐震」よりもコストがかかる他、制振装置を設置するため、間取りに制限がでてしまうところです。
――「免震」は、建物の下に装置を設置する構造だったとお聞きしました。
太田:はい、建物と基礎との間に免震装置を設置することで、揺れを逃がす構造です。住民の感じ方としては、大きくゆっくり揺れる感じです。耐震のように激しい揺れではないので、家具の落下や破損などは劇的に少なくなります。
ただ、コストがかかります。イメージとしては、「耐震」と比べ1.1倍ほど。これは、「免震」装置を設置するのに建物の下にスペースが必要だからです。通常の基礎工事に比べ、地盤を深く掘らなければなりません。ですので、敷地条件では工事自体が難しい場合もあります。また、技術力が必要な工事でもあるため、ゼネコン選びも重要です。

耐震性能を向上させる、長谷工が取り組む最新技術
――「耐震」構造は有名かと思いますが、「制振」・「免震」も昔からある構造なのでしょうか?
太田:調べてみると、「免震」のアイデアは19世紀末から国内外で提案されていたようです。20世紀初頭のアメリカでは、建物の下に石を敷き地盤から絶縁する方法が特許申請されたとの記録もあります。
一方、日本では関東大震災後に、さまざまな「免震」・「制振」構造が提案され、現代免震構造の日本第一号は1983年の八千代台免震住宅。一方、「制振」構造の日本第一号は1984年の日立本社ビルのようです(出展:都市・建築防災シリーズ4 制振・免震技術 鹿島都市防災研究会編著 鹿島出版)。
その後、1995年の阪神淡路大震災がきっかけとなり、「制振」・「免震」は急拡大していきます。おもしろいのが法隆寺の五重塔も揺れを逃がすという観点で免震構造の先駆けといわれていることです。免震の考え方自体は1400年前からあると思うと、感慨深いですよね。
――長谷工独自で行っている耐震性能を向上する技術などはありますか?
太田:高強度コンクリートに関する研究を芝浦工業大学 システム理工学部 環境システム学科 石川教授と共同で実施しています。高強度のコンクリートは大きな揺れに耐えられますが、大きな地震の際に表面が剥落し改修工事などが必要になる可能性があります。それを抑えるために、鋼繊維を混入させた高強度鋼繊維補強コンクリートというものを共同で研究しています。
高強度鋼繊維補強コンクリートであれば、地震後もある程度ひびなどを従来よりも抑えられます。この技術は現在実装に向け動き出しています。将来的に40階、50階の超高層マンションでの使用を想定しています。

▲地震が起こった際のシミュレーションは3Dソフトなどを使い建設前から何度も綿密に行っていく
――「制振」・「免震」に関わる最新研究はありますか。
太田:「免震」で言えば、長谷工などゼネコン数社で立ち上げた拡頭免震構造研究会で開発した、「拡頭杭免震構法(かくとうくいめんしんこうほう)」があります。この構法を活用すれば、課題だった免震における建設コストの高さ・工期の長さを改善できます。
「拡頭杭免震構法」では、径を広げた拡頭杭に直接免震装置を設置し、下部の基礎梁より薄い扁平な「つなぎ梁」で杭頭部を連結し、免震層の一体化を図っています。この構法では、杭頭を太くすることで地震の際に杭の頭部に生じる回転角を抑制する(建物への影響を軽減する効果がある)ことが可能になりました。さらに、つなぎ梁にしたことで梁の高さが小さくなり、掘削量が減り、基礎工事が簡略化でき、コストの削減と工期短縮を実現しました。

▲一般的な基礎免震構造は、免震装置(免震部材)の上下に基礎梁を配置するため、建設コストも高く、工期が長くなる傾向がある。「拡頭杭免震構法」はその構造を効率的に簡略化している
また、杭で言えば、ゼネコン9社で共同開発した「高強度鉄筋を用いた場所打ちコンクリート杭」という最新部材があります。これは、従来の鉄筋(強度が490N/mm2以下の鉄筋)よりも高い強度の鉄筋(強度が590~685N/mm2の鉄筋)を主筋として用いた場所打ちコンクリート杭です。強度の高い鉄筋を主筋に用いることで、主筋本数の削減と杭径を縮小できます。杭の合理的な設計を可能にし、施工性や品質向上を実現しています。

▲高強度の鉄筋を使用することで鉄筋数を減らし、杭径縮小も可能なため、掘削土量およびコンクリート量を削減。コストの低減につながる
――他にも耐震性能に有効な工法はありますか。
太田:当社と日興基礎、大亜ソイルが共同で開発した「HND-NB工法」も有効です。近年、集合住宅の高層化に伴い、杭の負担が大きくなっているため、地震時に発生する引き抜かれる力への対策として、杭の長さを伸ばしたり、杭径を大きくするなどの対応を行ってきました。この「HND-NB工法」は、杭の先端部にプラスして杭の中間部にも拡径部(本体部分よりも大きく広げた部分)を設けることで、地震への抵抗力をさらに向上させました。また、従来よりも杭長を短く、軸部径が細くても同等の支持力と引抜き抵抗力を得ることができるため、コンクリート量の削減、短時間施工を可能にしています。

▲既往工法と「HND-NB工法」の比較。杭の先端と中間に拡径部を設けている
――地盤・基礎関連で耐震性能を左右する事柄はありますか。
太田:当然、地盤が良いのに越したことはないのですが、地盤が悪いところであれば杭を太くするなどしてきちんと建物を支えることができます。そのため、特に注意することはないように思いますね。コスト面で負担は増えるかもしれませんが、どのような地盤であっても現在の技術であれば、基本的に建築基準法を満たす工法は可能ですのでご安心ください。

▲耐震補強のために柱やフレームを増やすことにより外観の美しさや居住性が損なわれることがあるが、長谷工はその点を技術力でカバーしている
既存マンションも美観を損なわずに耐震性能をアップ
――今までは新築マンションの耐震性能についてお聞きしましたが、既存マンションではどのような改修方法があるのでしょう。
太田:既存マンション向けには、当社の「長谷工ノンブレース補強フレーム工法」が有効です。
バルコニーの床スラブ下に幅広扁平梁と補強柱、補強間柱で構成した補強フレームを、既存フレームに直付けすることで耐震性を向上させることができます。眺望を妨げる筋交を用いずに補強するため、住人は住まいながら眺望を損なうことなく、耐震補強できます。
この改修工事は、もちろん長谷工マンションだけでなく、他のゼネコンが建設したあらゆる集合住宅で可能です。

▲「長谷工ノンブレース補強フレーム工法」のイメージ図
――最後に、読者に向けてマンションの耐震性能に関わることでアドバイスをいただけますか。
太田:基本的に建築基準法を満たしたマンションであれば、震度6強の地震で倒壊することは少ないと思います。当社施工のマンションは阪神淡路大震災でも倒壊率は0でした。ただ、耐震構造であれば激しい揺れは感じてしまいますし、家具が転倒することも多いです。そのため、身の安全の確保はもちろん、家具は転倒防止の策を講じるのが良いでしょう。
取材・文:太田祐一 撮影:石原麻里絵
WRITER
ディレクター/ライター。住宅関係の業界紙記者からキャリアをスタートさせ、独立後はさまざまな媒体で取材・インタビュー記事を執筆している。不動産だけでなくIT・デジタルマーケティングにも強み。X:@oota0329
おまけのQ&A
- Q.現在の建物は縦揺れにはまだ弱いといわれます。今後新たな技術は開発されるのでしょうか。
- A.太田:現状、縦揺れに対応できる技術はまだ研究段階のものが多いです。ただ、縦揺れに対応する3次元免震装置などは、各メーカーで日々研究開発されていますし、実証実験も多くなされています。近い将来、縦揺れにも効果を発揮する免震構造も一般に普及するかもしれないですね。また、ガス水道などの インフラを含めて町全体を免震化する構想などもあります。













 間取り変更リフォームで「できること」と「できないこと」。事例を交えてプロが伝授
間取り変更リフォームで「できること」と「できないこと」。事例を交えてプロが伝授