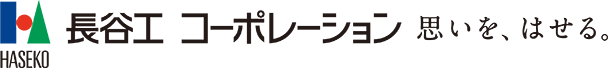サステナビリティ推進担当役員メッセージ

サステナビリティ経営への
「進化」と「深化」で、
持続可能な社会の実現に貢献します
経営管理部門サステナビリティ推進担当 兼
グループシニア事業管掌 吉村 直子
長谷工グループのサステナビリティへの基本姿勢
長谷工グループは、「都市と人間の最適な生活環境を創造し、社会に貢献する。」という企業理念のもと、これまで半世紀以上にわたりマンション業界のリーディングカンパニーとして歩んできました。この企業理念は、当社のサステナビリティ経営の出発点であり、持続可能な社会の実現に向けた不変の指針でもあります。
2025年4月、当社は新たな中期経営計画「HASEKO Evolution Plan」(2025年度~2030年度)をスタートさせました。これまで培ってきた技術力やお客様・取引先などとの信頼関係を「継承」しながら、刻々と変化する社会課題に対応するための「変革」を推進し、住まいと暮らしの創造企業グループとして新たなステージへの「進化」を遂げる―この進化こそが、長期的視点に立った企業価値向上と社会価値創造の両立を実現する道筋であり、長谷工グループが果たすべき責任でもあると考えています。
CSR経営からサステナビリティ経営へ
当社は、前中期経営計画「HASEKO Next Stage Plan(略称:NS計画)」(2020年度~2024年度)で「CSR経営の確立」を重要な経営目標の一つに掲げ、4つの取り組みテーマ—「住んでいたい空間」「働いていたい場所」「大切にしたい風景」「信頼される組織風土」—を軸とした活動を推進してきました。
この5年間で、私たちは着実な成果を上げることができました。一方で、この期間を通じて痛感したのは、従来のCSRアプローチだけでは限界があるということです。急速に変化する内外の情勢やステークホルダーからの様々な要請や期待に対して、サステナビリティ経営への「進化」と「深化」が不可欠であることを強く意識するようになりました。
2023年度から、当社は本格的にサステナビリティ推進への転換を開始しました。このパラダイムシフトは、これまでのCSRの取り組みを基盤としながらも、さらに一歩進んだ統合的なアプローチへの移行を意味します。個別の取り組みから発展させ、事業戦略とサステナビリティを一体化させることで、価値創造プロセスの中核にサステナビリティを位置づけ、長期視点に立った持続的成長を目指そうとするものです。
この転換期において、私たちはマテリアリティの見直しを行い、サステナビリティマネジメント体制の強化を進めました。また、非財務情報の重要性を再認識し、KPI設定の高度化、中長期目標の設定、包括的なロードマップの策定といった課題を整理した上で、より効果的なモニタリングやアウトカム評価の仕組みを構築するための検討や試行を行うなどしました。投資家との対話においても、当社の取り組みに対する理解と期待の高まりを実感しており、継続的改善への道筋をつけることを日々意識しています。
「HASEKO Evolution Plan」における取り組み
持続的成長とイノベーションを通じた社会課題の解決により真の価値創造を目指すためにも、「HASEKO Evolution Plan」の期間は特に重要なフェーズだと考えています。マテリアリティについては2023年に見直しを行い、13個を特定した上で、以下①~④を最重要マテリアリティとして推進しています。なお、社会情勢や当社事業を取り巻く環境の変化などによっては、あらためてマテリアリティの見直しを行うことも視野に入れています。
①気候変動への対応
気候変動への対応は、当社にとって最も重要な課題の一つです。脱炭素社会の実現に向けて、建設から不動産、管理運営まで、グループの全事業領域での取り組みを強化しています。
2021年に長谷工グループ気候変動対応方針「HASEKO ZERO-Emission」を策定するとともに、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言に沿って、気候変動対応に関する「ガバナンス」、「戦略」、「リスク管理」、「指標と目標」について開示しています。また、TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)提言に沿った情報開示も行い、生物多様性保全の観点からも持続可能な社会の実現と企業価値の向上を目指しています。
事業活動におけるCO2排出量の削減については、【Scope1】建設工程における低炭素燃料の活用などによるCO2削減、【Scope2】オフィスや建設現場で使用する電力の100%再生エネルギー化に向けた取り組み、【Scope3】環境配慮型コンクリートの開発・採用、ZEH-M(ゼッチ・マンション)の普及、集合住宅の木造化・木質化への取り組みなどを計画的に進め、これらに関する情報開示も積極的に行っています。
➁人的資本
人材こそが私たちの最も重要な資産であり、次世代を担う人材の成長は長谷工グループの未来を創造する原動力となります。
ダイバーシティ&インクルージョンの推進のため2023年にD&I推進室を新設し、これまでの女性活躍推進、シニア人材の活躍、障がい者雇用の促進、海外人材の積極登用といった取り組みをさらに発展させています。また、建設業界における技術継承の重要性を踏まえ、ベテラン技術者から若手への知識・技能の継承や、デジタル技術を活用した効率的な人材育成プログラムの充実を図るなどしています。
③人権の尊重
人権の尊重は、すべての事業活動の基盤でもあります。長谷工グループは、人権尊重の基本方針のもと、事業活動が人権に与える影響を継続的に評価し、改善しています。2022年に策定した「長谷工グループ人権方針」に基づき、人権デュー・ディリジェンスの取り組みを進め、協力会社などのステークホルダーとの協働により、人権尊重の実践を事業プロセス全体に深く根付かせることを目指しています。
社員教育や啓発活動についても、「人権ハンドブック」の制作・頒布や、「ビジネスと人権」などのテーマでの社内講演会の実施などを通じて、役職員の人権に対する理解を深めることに努めています。
④サプライチェーン・マネジメント
持続可能な事業運営の実現には、サプライチェーン全体での取り組みが不可欠です。協力会社をはじめとする取引先は共にサステナビリティを推進していく重要なパートナーであり、協力・連携体制を一層強化しながら、公正で責任ある調達活動に取り組み、持続可能な未来を創造するエコシステムの構築を目指しています。
2021年に制定した「長谷工グループサステナブル調達ガイドライン」に基づき、すべての協力会社に対してガイドライン遵守に関する同意を求めています。また、コンプライアンス、人権・労働、環境・安全といった重要な分野においては、主要協力会社に対して定期的に取り組み状況を確認し、サプライチェーン全体でのリスク管理の向上と持続可能性の強化を図っています。
長谷工グループの持続的成長とサステナビリティ
投資家をはじめとするステークホルダーとの継続的な対話は、当社のサステナビリティ戦略に欠かせない要素です。
投資家の皆様からは、情報開示の充実・強化に対する期待が高まっており、TCFD提言に基づく気候関連情報をはじめとして、人的資本に関する非財務情報の開示などについて、より透明性の高い情報発信と説明が求められていると認識しています。こうした要請は、当社にとって単なる義務ではなく、統合的思考を深め、マテリアリティをより明確にする貴重な機会であると捉えています。取締役及びサステナビリティ推進担当役員として、私の役割は、こうしたステークホルダーとの対話を通じて得られた期待や課題を経営戦略・計画に落とし込み実行していくこと、また、コミュニケーション戦略を通じてそれらの取り組みを継続的かつ丁寧に発信することだと考えています。
住まいと暮らしのリーディングカンパニーとしての当社の使命は、単に住宅という建物を提供することだけではありません。人々の生活を豊かにし、コミュニティを育み、次世代によりよい社会を継承していく―これらの実現こそが、サステナビリティ経営の真の目的であり、次の時代を担う人々への責任を果たすとともに、社会に貢献するレガシーを創造することにもつながります。
ステークホルダーとの共創により、サステナブルな社会の実現に向けて歩み続けること。それが、長谷工グループが提案する住まいと暮らしの未来であり、私たちの変わらぬ決意でもあります。皆様の期待にお応えできるよう、持続的な企業価値向上を目指して今後も真摯に取り組んでまいります。